目次
山口盆地に横たわる古層『大内文化』
山口を語るときに二つのファミリーを欠かしては語れません。
それは大内家と毛利家です。
大内家は室町幕府の周防と長門の守護大名であり、毛利家はその後中国地方の太守にのし上がった戦国大名です。
大内家が山口文化の古層だとすれば、毛利家は表層だといえるでしょう。
大内が山口で花開かせた文化は”大内文化”と呼ばれます。
これは京の都にあこがれた大内氏が地元の山口に都に近づこうとしてつくった宮廷文化です。
今も山口の特産品である外郎(ういろう)は、室町時代の大内氏揺籃期にほかの地方と違って米粉ではなく蕨(わらび)を原料とする外郎を始めたという由来があります。

山口の桜とホタルで有名な一の坂川は、大内が京都の桂川を模して造らせたものです。
大内氏が”西の京”と呼ばれるほどに繁栄した街を山口の盆地に築けたのは石見銀山と博多の存在が大きいでしょう。
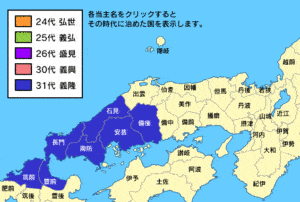
「歴史の町山口を甦らせる会」制作 「大内文化の遺産」サイトより
大内氏は義隆の時代には西は今でいう福岡北九州、東は広島島根まで中国九州にまたがる7カ国を勢力下に置いていました(大内文化の遺産参照)。
版図でいえば毛利元就の最大版図のほうが大きかったかもしれませんが、元就は執拗に関門海峡を越えて博多がある北九州を奪取しようとしましたが、最後までその野望は果たせませんでした。
博多は大陸明との勘合貿易の拠点で、大内義興(よしおき)の時代に室町幕府から貿易を任され、以後貿易の利益を大内氏は独占してきたのです。
大内氏はもともと百済の国の第3皇子琳聖太子が日本に帰化し開祖したもので、以来32代にわたって山口の大内御堀の地名から大内氏を名乗ってこの地を治めてきたのです。
このため半島や大陸との交易によって富を築き、応仁の乱で灰燼状態となった京の都から逃れてきた僧侶や公家などの文化人を保護したことによって、山口の盆地に雅(みやび)な文化を花開かせたのです。
長門深川「大寧寺」で大内義隆が自刃

大内義隆は16代目で最後の守護大名になります。
守護職であった大内義隆は家来の守護代である陶隆房(すえたかふさ)に謀反を起こされて滅びます。
これが世にいう「大寧寺(たいねいじ)の変」です。
下剋上というと信長が明智光秀にやられた本能寺の変が有名ですが、この大寧寺の変はそれに匹敵するといわれています。
室町幕府の崩壊の引き金をひいて戦国時代の幕開けを実現したという意味ではエポックメイキングな出来事でした。
義隆の滅びるまでの経緯をみると、義隆は大名としてみれば残念ながら愚鈍であったと評価せざるを得ないかもしれません。
陶隆房は8月20日に挙兵、兵数5000から1万で本体は徳地方面から、別動隊は防府方面から山口を目指して侵攻しました。

23日には山口では陶隆房侵攻のうわさが駆け巡っていましたが、義隆は酒宴の真っ最中、27日にはなんとものんびりとした話ですが来客のための能興行にいそしんでいました。
陶侵攻の注進を受けようやく大内氏館をでて山麓の法泉寺に本陣を構えましたが、兵数はわずかに2千から3千といわれ、それも逃亡兵が相次いだといいます。
付き従った重臣といえるものは、わずかに冷泉隆豊ぐらいでした。
そのため義隆は山口を脱出して長門に逃亡し、仙崎港から石見の吉見正頼を頼って舟を出そうとしますが、あいにくの暴風雨のために断念。

仙崎港
引き返した義隆は深川の大寧寺に入ります。
義隆は境内に入る前に髪を整えようと兜(かぶと)を脱いで参道脇の岩に兜をかけます。
これが「兜かけの岩」です。

かぶと掛けの岩
その傍らにある池で顔を写そうとしましたが、水面に顔が映らなかったため、義隆は自分の運命を悟ります。

姿見の池
9月1日の午前中に住職から戒名を授かると自害、ここに中国地方の名門大内家は事実上滅亡したのです。
義隆の辞世の句は、
討つ人も 討たるる人も諸(もろ)ともに 如露亦如電(にょろやくにょでん) 応作如是観(おうさにょぜかん)
最後の言葉は禅語なのですが、簡単に言えば、討つ人も討たれる人も人生は短く儚いものだという諦念をうたったものです。
実際義隆を討った陶隆房もその後わずか6年後、厳島(いくつしま)の戦いで毛利元就に敗れ自害します。
ところで大寧寺の変のあり様をみると、義隆はなぜ先手を打って陶隆房を討たなかったのかと思われるかもしれません。
実際に冷泉隆豊は隆房を誅殺するよう何度も進言していましたが、義隆はそれを無視したのです。
というのも陶氏というのはもともとは大内氏の一族であり、代々守護代を務めてきた名門で、身内といっても良い間柄だったのです。

大寧寺山門跡
応仁の乱などで大内氏が中央に度々出兵して自国を留守にしてい時は守護代である陶氏が代わりに地元を治めてきたのです。
またこの時代、室町幕府の権威は失墜していたとはいえ下剋上という事変までは起こっていませんでした。
義隆にしても尼子晴久との敗戦(月山富田城の戦)以後仲が悪くなったとはいえ、まさか自分がやられるとは考えていなかったのかもしれません。
大内文化とは言い換えれば公家宮廷文化であり、本来は武家であるはずの大内家自ら公家化してしまったことが、大内氏滅亡の大きな要因のひとつとなったのでしょう。
お寺の本堂の横の脇道を少し上ると大内家と最後まで付き従った家来たちの墓があります。

特に最後まで奮戦した冷泉隆豊の墓標は大内義隆の隣にあります。
隆豊は義隆の介錯をした後、再び力戦奮闘したうえで自害します。
隆豊の辞世の句は、
見よや立つ 煙も雲も半空(なかぞら)に さそいし風の 音も残らず
この大寧寺付近に防長三奇橋のひとつであるその名も盤石橋(ばんじゃくばし)があります。

この石橋は最初は寛文8年(1668)に建架され、そのあと宝暦14年(1764)に再建架されていることがわかっています。
全長14,2mで、大小の自然石のみで構成されています。
このような工法を突桁式工法と呼びますが、これはドイツで開発されたゲルバー橋(1868)よりも早いことで評価の高い橋です。
側面からみると、なんだかウミガメの顔みたいに見えてくるのは私だけでしょうか。
またここには釈迦三尊と十六羅漢像の石仏群があります。

もともと前方の大寧寺川対岸にあったものを平成17年に移設したものですが、延宝5年(1677)に益田氏が山門を再建したときに造られたと考えられています。
この羅漢像、表情がとても写実的でみててあきません。
益田氏は石見益田を拠点にしていた名門の武家です。
もともとは中央から下った石見守藤原国兼(くにかね)が開祖といわれており、そのまま土豪化したと考えられています。
益田氏は大内氏に従属しながら所領を守ってきましたが、大寧寺の変で義隆が討たれると陶晴賢傀儡の大内氏につきます。
しかし厳島の戦いで晴賢が討たれると毛利に所領を攻め込まれて以後は毛利氏に従うようになります。
関ヶ原の戦いで毛利が防長2か国に減封されると益田氏も石見を離れて長門須佐に所領を持ちます。
以後益田氏は長州藩の永代家老として幕末まで命脈を保ち続けるのです。

萩藩永代家老 須佐益田家 三十二代 益田玄番元宣 嘉永二年没 以下略
また大寧寺の梵鐘(ぼんしょう)には筑前は福岡の麻生氏の影響がみられます。

この鐘、もともとは鎌倉時代から鋳物の産出で有名だった福岡の芦屋津にある長福寺のものだったそうです。
そこは麻生氏の所領で、麻生氏は大内殿有名衆の筆頭に数えられる実力者でした。
麻生氏の分骨堂が数基大寧寺にあることなどから、大寧寺と麻生氏は因縁が深いために梵鐘がもたらされたと考えられています。
このように大寧寺は大内に従っていた毛利、益田、麻生と福岡から石見周辺にまたがる勢力の影響下にあります。
それだけ大内氏の勢力が大きかったことがわかります。
大寧寺の隣には豊川稲荷神社もあります。


音信川沿岸に長門湯本温泉

長門には長門湯本という、ほどよくひなびた風情のある温泉街があります。
ほとんどの方は車で来られるのですが、美祢線で長門湯本駅からでも行けます。

長門湯本駅は平屋建ての趣のある駅舎です。
そこから温泉街のほうに5分程度歩くと音信川(おとずれがわ)が見えてきます。
そのまま川に沿って歩くと長門湯本の温泉街が、右手に歩くと大寧寺があります。
川の左手に星野リゾートの旅館「界・長門」が来年3月に開業予定となっています。

長門湯本に久々の大型旅館の進出ということもあり、地元では観光の起爆剤となるか期待と不安でいっぱいだそうです。
そこから少し先に老舗でこの温泉街を引っ張ってきた大谷山荘があります。

プーチン大統領が宿泊したことでも有名ですよね。
大寧寺川や音信川は合わさって深川になりますが、その支流群にはこの時期ほたるが乱舞します。
ほたるの光を見ながら山口の地に雅な文化を光らせた大内氏の栄華に思いを寄せてみてはとおもいます。
さて大寧寺を舞台に、大内氏と諸勢力の簡単な歴史を語ってきましたがいかがでしたでしょうか。
大内氏の文化は知らないところで山口に根付いていて、まさに山口の古層ともいえる存在です。
次は山口文化の表層である毛利家萩藩の歴史を毛利博物館で6月1日から開催されている企画展「萩藩とは?」の内容から紹介したいと思います。







