目次
琵琶法師が吟じる「耳なし芳一」の正体とは

赤間神宮(あかまじんぐう)は下関は関門海峡に面して、壇ノ浦の戦いで入水し崩御した安徳天皇を祀る神社です。
神宮になる前は阿弥陀寺という寺でしたが、明治維新の廃仏毀釈を機に神宮になりました。
そのため神宮の住所は下関市阿弥陀寺町となっています。
安徳天皇を偲ぶ御祭りで有名なのは「先帝祭(せんていさい)」ですが、怪談で有名な芳一を記念するのが7月15日に行われた「耳なし芳一まつり」です。
ところで芳一のような琵琶法師は平家物語(=平曲)を吟じて諸国を漫遊していました。

壇ノ浦古戦場
平家物語は今でこそ平家についての物語とされていますが、もともとはこの名前で呼ばれていたわけではなく、該当する時代の元号である治承物語(じしょうものがたり)となっていました。
また作者は確定されていないものの鎌倉時代初期に活躍した歌人で公家の藤原行長(ゆきなが)ではないかといわれています。
これは徒然草の作者である吉田兼好が以下のように書き記しているからです。
後鳥羽院の御時、信濃前司行長稽古の譽ありけるが(中略)この行長入道平家物語を作りて、生佛といひける盲目に教へて語らせけり
平家物語は仏教的な無常観で語られており、作者が仏教思想に深く通じていることは作者の正体を知るうえで大事な要素です。
祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらは(わ)す。
おごれる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。
たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。
行長の家族や親族が法然と深いかかわりがあったことなどから、行長自身に深い仏教の知識があったと思われます。

ビルの合間から見える関門橋
また平氏源氏どちらにも組していない中立的な人物であることなどを考えると、藤原氏である行長の蓋然性は高いと思います。
この平家物語を吟じて諸国を漫遊していた琵琶法師についてすこし話したいと思います。

赤間神宮の境内にある芳一堂
琵琶法師が活躍した鎌倉時代など中世において、諸国を漫遊する資格は幕府や朝廷によって担保されていました。
琵琶法師のみならず、まじない師などは中世を旅する「道々のもの」といわれていました。
琵琶法師は目の見えない盲人の職業でしたが、そもそもの起こりは弘仁(こうじん)元年(810年)に即位した仁明(にんみょう)天皇の子である人康(さねやす)親王が失明し、そのために出家して山科(やましな)に隠棲したときに始まります。
親王は隠棲の土地で同じ盲人たちを集め、琵琶や管弦、詩歌などを教えました。
親王が亡くなった時に、側に使えていた盲人に検校(けんぎょう)と勾当(こうとう)の二官が与えられました。
これが検校という盲官の始まりといわれています。

防府市出身の彫刻家押田政夫氏作の芳一像
人康親王が坐って琵琶を弾いたという琵琶石は、後に盲人達により琵琶法師の祖神として京都の諸羽(もろは)神社に祭られています。
検校は盲官の最高位にあたり、以下位階順に別当(べっとう)、勾当、座頭(ざとう)となります。
時代を経るに従い順位はさらに細かく分かれ、73の位階に分かれるようになり、芸の習熟度にしがたって申請してその職階を得るようになっていました。
勝新の映画で有名な「座頭市(ざとういち)」は任客で座頭の”市”という人物が活躍する映画のことです。
さてこのように琵琶法師というものが生まれたのですが、南北朝時代に明石覚一(あかしかくいち)という僧侶がいました。
足利尊氏の従弟(じゅうてい・年下のいとこ)で姫路の書写山(しょしゃざん)で僧侶だったのですが、中年になってから突然失明し、そのため琵琶法師となりました。
彼は自分の屋敷に盲人たちの自助組織である座(当道座)を設置します。

そして自ら惣検校(そうけんぎょう)、もしくは明石検校ともいわれている、となって江戸時代まで続く検校制度を創始したのです。
この覚一が耳なし芳一のモデルになったといわれています。
覚一は一方流(いちかたりゅう)を創始した坂東如一(ばんどうにょいち)の弟子で、琵琶の達人で一方流の中興の祖ともいわれます。
平曲にはもう一つ八坂城玄(やさかじょうげん)らによる八坂流という流派があるのですが、こちらは旧来の作法を厳格に守る流派です。
一方流の法師は名前に”一”もしくは”市”の字を含むこととし、八坂流は名前に”城”の字を含みます。
というのも如一と城玄の共通の師匠に城一という人物がいて、その人の名前の一と城をそれぞれ受け継いでいったからです。
なので芳一や座頭市も一方流の法師ということになります。

挙式などが行われる龍宮殿。この日は薩摩琵琶の櫻井亜木子氏のライブも行われました。
芳一の「芳」は音読みでは”ほう”ですが、訓読みでは”かぐわしい”とも読みます。
覚一の覚に芳の字を当てた可能性もあります。
もしくは一方を逆にした方一に芳一という字をあてたのかもしれません。
覚一はもともと足利氏の出ということもあり公家や武士を相手に平曲を吟じるとともに、天皇・上皇・親王らのための御前演奏をおこなうことが多かったといいます。
このようなところが覚一を芳一のモデルにしたのでしょう。

おそらく一方流の後年の弟子たちが、平家の亡霊までもが涙を流すほどの平曲の達人であるという、一方流の宣伝話として世間に流布させたのが「耳なし芳一」の始まりではないかと思います。
実際に南北朝から室町時代にかけて覚一以下一方流が平曲を広めた功績は大きかったといいます。
ただ現代に伝わるような形で耳なし芳一の物語を広めたのは、やはり小泉八雲の小説「怪談」の影響が大きかったわけですが。
琵琶は江戸時代にはやった三味線に駆逐されないで生き残ります。
しかし明治になると琵琶法師=平曲師は制度の保護からはずれたため、鍼灸(しんきゅう)や按摩(あんま)という技能を身に着けて生業にしていくことになります。

ところで芳一は身体中に般若心経(はんにゃしんぎょう)を書き込んで平家の亡霊から身を隠したのですが、これはなぜなのでしょうか。
実は当時から在家信者の間で般若心経は悪霊の力を”空じて”くれるという信仰があったのです。
このためお守りとして所持したり、病気の時は平癒を願って写経したりすることもありました。
色不異空、空不異色、色即是空、空即是色
色は空と異ならず、空も色と異ならず、色即ち空なり、空すなわち色なり。
般若心経で有名な色即是空(しきそくぜくう)とは、色(宇宙に存在するすべての形や物質)は空(恒常的な実体などない)であると解釈されます。
つまりこの世には縁起(因果・関係)しか存在せず、実体などは因果が失われれば消滅してしまうという意味です。
芳一は般若心経を身体に書き込むことで、通俗的な解釈ですが、自分を空ずる=透明化したというわけです。
平家物語の根底に仏教の無常観があるというのはこの般若心経を見てもわかりますし、耳なし芳一の話にもそれが埋め込まれているわけです。
赤間神宮の境内には芳一像の横に平家一門を祀った「七盛塚」があります。
平教盛、平知盛、平経盛、平教経、平資盛、平清経、平有盛、平盛継、平時子(従二位尼)らの名前が刻まれています。

ここにはない清盛と六つの盛の字のついた石を合わせて七盛というわけです。
伊勢平氏には墓石ではなく名前の付いた石を並べるという風習があり、この塚もそれにならっています。
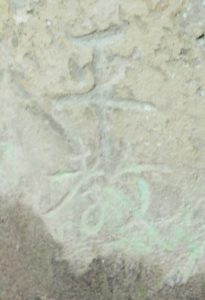
平教(盛)
平家物語で平家一門が滅んだことになっていますが、正確には平家の一氏族である清盛率いる伊勢平氏一族が滅んだということです。
例えば源頼朝を支え、後に執権となって事実上鎌倉幕府を差配した北条氏なども平氏ですから、平氏すべてが滅んだわけではありません。
塚の隅に高浜虚子が詠んだ句が刻まれた石碑がたっていました。

七盛の 墓包み降る 椎(つい)の露(つゆ)
---高浜虚子
「耳なし芳一まつり」で薩摩琵琶、筑前琵琶を聴く

まつりでは夕方の18時よりまず水がはられている本殿内で、神主さんによる神事が執り行われました。


その後、青山旭子氏による筑前琵琶の演奏が始まります。


次に櫻井亜木子氏による鶴田流薩摩琵琶の平曲が吟じられました。

櫻井さんはあの小椋佳さんのコンサートツアーにも参加している方で、京都の六波羅蜜寺でも演奏されています。
六波羅蜜寺は平家一門の邸宅が立ち並んでいた場所で清盛の供養塔があり、また清盛の娘徳子が安徳天皇を出産した地でもあります。
また文化庁の文化交流̪使として世界16カ国に派遣され、今年もチュニジアで演奏される予定だとおっしゃっていました。

櫻井さんはこの後、龍宮殿においてもライブでほぼ1時間にわたって耳なし芳一を吟じてくれました。
耳なし芳一の実際の舞台で、本物の琵琶法師さんの物語を聴くというのはとてもぜいたくな体験でした。
素人なので筑前琵琶と薩摩琵琶の細かい違いなどはわかりませんでしたが、お二人とも凛とした空気のなかで力強く耳なし芳一と平家物語を短くまとめた話を滔々と吟じていました。
昔のように盲目の方で琵琶法師をされている人は今ではだいぶ少なくなっていて九州の一部に残っている程度だそうです。
その代わりにこのように女性の方が琵琶法師として活躍しているのはすばらしいことですよね。
この記事を読んで来年こそはと思われた方は是非お越しください。
神宮前のゲストハウス”UZUHOUSE”で一休み

芳一まつりの前にランチでもとろうとおもったのですが、赤間神宮付近では適当な場所がありません。
なので唐戸市場や海響館がある市街地のほうまで行こうかなと思ったのですが、ぶらぶら歩いているとすぐ前にUZUHOUSE(ウズハウス)という看板が目に入りました。
ゲストハウスの1Fに簡易なカフェが併設されているようでしたので入ってみました。
1Fはロビー兼休息スペースになっていてコーヒーや軽食もいただけるようです。

2Fにあがるといくつかのテーブルやソファやイスが置いてあって、会議や自習などをする多目的ルームでした。
軽食もいただけますよ。



アイスコーヒーとサルサソースがかかったホットドックをいただきました。おいしかったです。

この部屋からの関門海峡の眺めはすばらしいので骨休みにでも寄ってほしいと思います。


3Fから上は客室となっていてみれませんでしたが、いつか泊まってみたいと思います。
清潔で明るくて場所も下関市街地まで自転車ですぐなので、女性にもお勧めしたい場所です。
もともとは割烹旅館だったところをフルリノベーションしてゲストハウスとして再生したようです。

さて、今回は耳なし芳一まつりということもあり琵琶法師を中心に話しました。
次に赤間神宮を取り上げるときは先帝祭になりますので、その時は安徳天皇について語りたいと思います。







