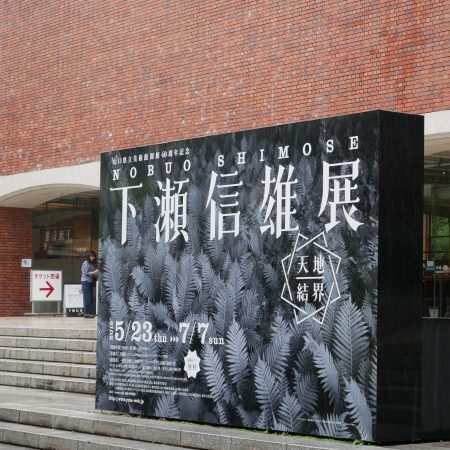防府天満宮の御神幸祭である裸坊祭

11月23日と24日の二日にわたって防府天満宮で御神幸祭(ごじんこうさい)が行われたので取材してきました。
この御神幸祭は、別名裸坊祭(はだかぼうまつり)といわれ、もともとは中央政界で左遷され失意の下で亡くなった道真公の御霊を慰めるために行われるものです。
防府天満宮の説明によれば以下のようなものです。
都では道真公に対し左遷の詔の破棄、さらには正一位太政大臣が送られましたが、防府の道真公のお御霊に直接の「無実の知らせ」はなく、道真公のお心が晴れることはありませんでした。
ところが漸く創建百年に当たる寛弘元年(1004)10月15日、一条天皇の勅使が防府に使わされ勅使降祭(お御霊を慰める祭典)が斎行され、初めて天皇から「無実の罪」が奏上されたのでありました。
このことを待ち続けられた道真公のお御霊はどれだけ安堵されたことでありましょう。
御神幸祭はこの勅使降祭を起源とし、その時以来「無実の知らせ」を伝えるお祭りとして連綿と受け継がれ、防府の天神様にとって崇敬の源となる最も重要なお祭りとなりました。
この御神幸祭の前祭として、前回記事にした花神子社参式があります。
それではなぜこの祭が裸坊祭と呼ばれるのでしょうか。
それはこの祭りの当初は大行司・小行司や限られた家柄の者だけに渡御の奉仕が許されましたが、江戸時代後期になると天神信仰の高まりとともに、一般奉仕者の参加意欲も高まりました。
身の潔白が証明された一般奉仕者の参加も許されるようになったのですが、そのために佐波川で水垢離をとったままの姿で奉仕しましたので、その姿から裸坊と呼ばれるようになったのです。
ちなみに佐波川と天満宮との縁は深いものがあります。
現在では白装束に身を包んだ一般の奉仕者たちが裸坊として、祭りに参加しています。
裸坊祭は天満宮の祭式のなかでも最も大規模なもので、参加人数も出店の数も群を抜いています。
夕方の6時に本殿を出仕する神輿と御網代輿である御車は街中を抜けて御旅所を経て、3時間後の9時ごろに本殿に戻ってきます。
その間、一般観光客の方は境内で飲み食いするわけで、マーケティングの面でもよくできた祭式だと思います。

「兄弟、ワッショイ」の掛け声とともに、天満宮の長い石段を御車の上部と車輪がそれぞれ別個に切り離されて降りていきます。
石段の途中にある大専坊跡にはこの裸坊祭を司祭する大行司、小行司が見守っています。

御網代輿は重さが500キロあり、その巨大な御輿が拝殿の階段を下り、楼門を経て58段の大石段を滑り降りる様は壮観です。




動画のほうもリンクしておきます。
この投稿をInstagramで見る
しばらくして神輿とは天満宮に戻ってきます。
今度は石段上をみんなの力で引き揚げていきます。
そして天満宮の本殿の中にまで引き入れられていきます。


同日行われた山口市三大祭りのひとつ山口天神祭

天満宮の裸坊祭と同日の日中に山口市内にある古熊神社で山口市三大祭りの一つに数えられる山口天神祭が行われました。
ところで”天神”とはどういう意味でしょうか。
天神とは「天満大自在天神」の略称で、道真公の没後の神号のことです。
天満宮の祭神であり、学問の神様(雷神)でもあります。
この古熊神社のように山口県内の神社の多くは道真公を祭神とする天神社としての性格を持っています。
山口市の商店街といえば道場門前商店街、略して道門商店街ですが、この天神祭は近傍の八坂神社と古熊神社を出発した行列がこの商店街を中心に徘徊します。
古熊神社の由緒ですが、応安六年に大内弘世が京都の北野天神を勧進して北野小路にあったものを、元和四年に毛利秀就がこの地に遷宮したものです。
祭神は菅原道真公で、本殿は室町時代のものをこの地に移築したものです。

この古熊神社から神輿が出発しますが、車輪のついた神輿が石段を下る様は、天満宮の裸坊祭と同じ構図です。