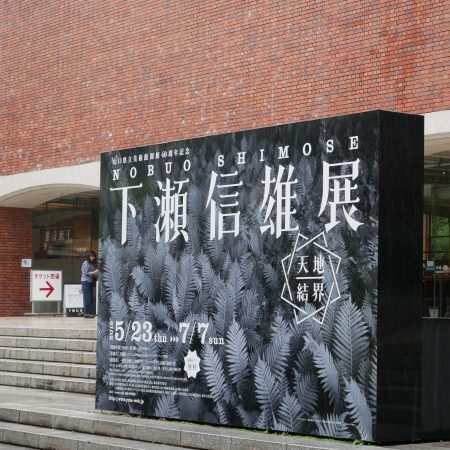目次
佐波川の鮎漁の豊漁と安全を祈るお祭り「金鮎祭」

桜が散り、GWも終わり、新緑のまぶしい季節になりますと、佐波川(さばがわ)で鮎漁(あゆりょう)が6月から解禁されます。
佐波川は山口県中部を流れる一級河川で、島根県との県境に端を発し、防府市北西部を通過して周防灘の河口まで続いています。
佐波川は鯖川とも書きます。
佐波川ではサバが実際によくとれ、周防の国の特産品だったのです。
この佐波川での鮎漁の豊漁を祈って解禁日に先立って防府天満宮で行われるのが金鮎祭(きんあゆさい)です。
菅原道真公との由緒

それではなぜ防府天満宮で佐波川の豊漁を祈る式典が行われるのでしょうか。
それは天満宮が奉る菅原道真公が関係しています。
菅原道真公を奉る天満宮で有名なのはこの防府天満宮のほかに京都の北野天満宮、九州の太宰府天満宮などがあります。
太宰府天満宮は道真公が薨去(こうきょ)された地に、北野天満宮は都の人々が道真公の祟りを畏れてそれを鎮めるために建てられたものです。
それでは防府天満宮は道真公とどのような由緒(ゆいしょ)があるのでしょうか。

道真公が中央政界での政争に敗れ、大宰府に左遷されて向かう途中に防府の勝間の浦に船旅の途中で立ち寄ったそうです。
そのとき道真公は、「此地未だ帝土を離れず願わくは居をこの所に占めむ」とおっしゃられたといいます。
意味は、この地は西のはずれであるがいまだに帝のおわす都と地続きである。無実の知らせが京より来るのを待つためにここに住みたいものだ、というものです。
道真公が薨去されたときに、神光が現れ、酒垂山(現・天神山)に瑞雲が棚引き人々を驚かせたといいます。
そこでこの地の人々は翌年の延喜4年(904)道真公の願われた通り、御霊魂の「居」を「この所」である松崎の地に建立して「松崎の社」と号しました。
これが現在の防府天満宮の由緒になります。

佐波川漁業協同組合の皆さん
道真公は防府を訪れた際、地元の人々に手厚くもてなしてもらった御礼に、金の鮎12尾を同じ一族で国司の土師信貞へ託していました。
土師信貞はそれを神前に供えましたが、残念ながら3度の焼失ですべての尾を失ってしまいました。
2002年の天満宮1100年式年の大祭の際に、それを今一度復活させて神前にお供えしようということになり、改めて12尾すべてが復元されたのです。
それから毎年この時期に道真公に金鮎を献上する儀式を行っているのです。
金鮎祭は周防国分寺住職との神仏合同祭

金鮎祭は周防国分寺の住職さんも一緒になって執り行われます。
なのでこの儀式は神仏合同なのです。
神仏合同の儀式というのはなかなか見られないものなのでとても新鮮なものでした。
周防国分寺は、天平13年(741)聖武天皇の勅願(詔)によって諸国に建てられた国分寺のうちの一つです。
道真公がおそらくは立ち寄られたことは確かだと思います。
国分寺は天満宮からほど近いところにあり、天満宮、阿弥陀寺と並ぶ防府の観光資源でもあります。
周防国分寺が貴重なのは、金堂の伽藍の配置が奈良時代創建時のまま残っていることです。
是非、天満宮を訪れた際は近辺の国分寺も訪れてください。
さて、佐波川の組合の皆さんから提供された若鮎は、まず国分寺住職の手に渡された後、宮司の手に渡されます。
宮司はそれを神前に供えて豊漁を祈願するのです。


巫女さんによる優雅な舞が披露されました。

関係者でない限りなかなか金鮎祭の儀式を真近で見る機会はありませんが、朝の10時過ぎに境内で待っていますと、参集殿のほうから献上される鮎が運ばれてきますので、その瞬間をみることはできます。
金鮎祭が終わると、今度は川の幸から土の幸を祈る行事、お田植祭が6月30日に天満宮で行われます。
芳松庵で裏千家による奉祝茶会

防府天満宮には芳松庵(ほうしょうあん)という茶室があります。
そこで裏千家による奉祝茶会が開かれていました。
防府天満宮が祀(まつ)る道真公にはお茶の文化を復活させた功績があります。
お茶の文化が中国から宮廷にはいってきたのは平安初期のころですが、その文化は一時途絶えようとしていました。
そうしたときに道真公はお茶の文化の調査研究を指示して復活せしめたのです。
道真公はそのため茶聖菅公として知られ、そのことを記念する茶室を新たに作ったのです。
庭園の一角には梅の形をした台座が置かれていました。とてもかわいらしいですよね。

芳松庵の境内には、周防一といわれる楠(クスノキ)があります。
樹齢が800年、幹周が5.6m、高さが27.5mといいますから見上げるほどの大樹です。

毛利元就も尼子との戦いで天満宮内の大専坊(だいせんぼう)に本陣を置いたといいますから、この楠を見ているわけです。
そう考えると歴史の証人ともいえる大樹なのです。
そもそもなぜ鮎漁は解禁時期が決まっているの?

ガイムさんによる写真ACからの写真
山口県は三方を海に囲まれて、海の幸豊かなことで有名で、例えば下関のフグなどは全国区です。
しかし同時に川魚もおいしいのです。
中でも鮎料理は美味しい料理です。
これは山口にはきれいな川がいくつも流れているからですね。
なぜきれいな川がおいしい川魚をはぐくむのかというと、餌となる良質の珪藻類(けいそうるい)が良く育つからです。
鮎は幼魚の時以外は草食で、石に付着しているぬるぬるした珪藻類、つまり苔を食べて成長します。
山口県内で有名なのはこの佐波川と並んで岩国の錦川での鵜飼による鮎漁があります。
島根県の津和野まで行くと、高津川(たかつがわ)での天然鮎が有名です。
鮎は食べられる季節が限定されています。
これは鮎という魚が「年魚(ねんぎょ)」と呼ばれる1年しか生きられない魚だからです。
鮎は毎年秋になって卵を産むと死んでしまうのです。
なぜ死んでしまうかというと餌である珪藻類が冬にはなくなってしまうからです。
鮎は秋に孵化した後、川の流れに乗って海に出ます。
海に出た幼魚はプランクトンなどを餌にして成長します。
ある程度成長すると3~4月ごろにかけて、今度は海から川へと遡上して石についた珪藻類を食べて大きくなるのです。
このため鮎漁の解禁は6月に入ったころぐらいになるわけです。
佐波川でも岩国の錦川でも6月1日が解禁日になっています。
美味しい川魚を食べるためには新鮮な素材と焼きの技術が必要

鮎は別名「香魚」といわれるぐらい、新鮮な鮎からはスイカのようなにおいがするといいます。
これは鮎の不飽和脂肪酸が魚のエラや皮膚表面に付着した酵素によって分解された際にでるにおいだといわれています。
新鮮な鮎には川魚にはつきものの生臭さがないのです。
昆虫を主食とする川魚は内臓は取り除く必要がありますが、鮎は草食なので良く火を通せば内臓まで食べられます。
美味しい川魚料理にはきれいな川で育った新鮮な魚と川魚特有の焼きの技術が必要になります。
そのためそれぞれの鮎漁の名産地では川魚専門のお店があります。
鮎は時期によって味わい方が違ってきます。
解禁当初の若鮎は引き締まった身のおいしさが、8月ごろには良く育ち脂ののった身のおいしさがあります。
是非それらを探して自然の恵みと漁師さんの努力に感謝しながら川魚を堪能してほしいと思います。